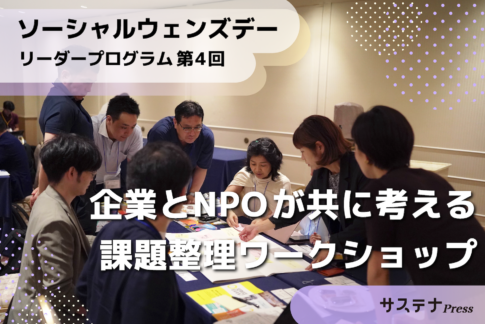少子高齢化やデジタル化の加速、産業構造の変化を背景に、近年は「リスキリング」が注目されるようになりました。政府もGX人材育成や人材開発支援助成金などの施策を打ち出していますが、注目度の高さに比べ、理解・実践にはギャップがあるという現場も少なくはありません。
本記事では、リスキリングという社会課題に対する具体的な取り組み・事例を紹介し、私たち一人ひとりが考えるべきポイントを探ります。
社会課題としての「リスキリング」
リスキリングは単なる「学び直し」ではありません。産業構造の大きな転換期において、新たな環境で生き抜くための能力を獲得することを意味します。特に今、この課題が重要視されている理由には、時代の変化が大きく関わっています。
製造業からIT産業へのシフト、気候変動対応人材の需要増加、ヘルスケア分野の拡大など、産業のあり方そのものが変化する中、これらに対応すべく「変わる企業」と、既存のスキルや知識だけでは対応できず「取り残される個人」との間の分断が広がりつつあります。
日本においては特に、教育・労働・福祉の領域が政策的にも実務的にも切り離されてきた歴史があります。学校教育を終えたあとの学び直しの機会が限られ、一度就職した企業や業界から移動することが難しい労働市場の硬直性、そして職を失った際のセーフティネットが不十分という構造的課題が存在しています。リスキリングはこれらの課題を横断的に解決する必要性を示しているのです。
異なる立場・規模から見る、3社のリスキリング
社会の変化に対応するために、企業はどのように「リスキリング」を実践しているのでしょうか。ここでは、事業規模も業種も異なる3社(キヤノン、ダイキン工業、八天堂)の取り組みを紹介します。
キヤノン株式会社|希望のキャリアを叶えるキャリアマッチング制度
キヤノンは、リスキリングを中長期的な人材戦略の柱に据え、社員一人ひとりのキャリア転換を支援する制度を整備しています。中でも特徴的な取り組みは、未経験分野への挑戦を後押しする「キャリアマッチング制度」の導入。異なる部署や業務への異動を希望する社員に対して、事前の研修プログラムを用意するなど、新たな職務を学び、チャレンジできる環境を整えています。
また、同社は2018年に「CIST(Canon Institute of Software Technology)」というソフトウェア技術者向けの研修施設を開設。デジタル領域のスキルアップや、新しい専門分野への転換を社内で実現できるよう、継続的な育成体制を整えています。
社員の“やりたいこと”と企業の“必要な力”をマッチングさせ、双方にとって納得感のあるキャリアを築くこの仕組みは、リスキリングを「個人の挑戦」として位置づける好例と言えるでしょう。
ダイキン工業株式会社|社内大学で育てる“本気のデジタル人材”
製造業の中でもDXへの取り組みで注目されるダイキン工業は、2017年に社内大学「ダイキン情報技術大学(DICT)」を設立し、社員のリスキリングを本格化させました。
DICTは、社内選抜された社員を対象に2年間の集中教育プログラムを実施するもので、1年目はAI・IoTなどの技術基礎を学び、2年目は実際の業務に基づいた課題解決型プロジェクトに取り組みます。
特徴的なのは、教育の内製化です。DICT修了生がその後、後輩の講師役となって知識と経験を社内に還元していく仕組みがあり、リスキリングが一過性の取り組みにとどまらず、企業文化として根づくよう工夫されています。また、修了生の中には外部ベンチャー企業に出向し、最先端の現場で実践経験を積む人もおり、学びと業務の接続が非常に高いことが特徴です。
参考:AI分野の技術開発や事業開発を担う人材を育成する社内講座『ダイキン情報技術大学』を開講|ダイキン工業株式会社
社内大学で学んだ優秀な新人を出向させる“ダイキン流データ活用人材育成術”とは?|ダイキン工業株式会社
株式会社八天堂|老舗企業が挑む、現場に根ざした“学び直し”
昭和8年創業、くりーむパンで知られる広島の老舗・株式会社八天堂も、リスキリングに積極的な中小企業の一例です。
八天堂は広島県の「リスキリング推進宣言」に賛同し、全社員のスキル向上を支援する仕組みづくりを進めています。パン製造・販売にとどまらず、接客、商品開発、IoT活用などの幅広い分野において、現場に即した研修や外部との連携による学習機会を提供しています。
特にユニークなのが、社員の興味・志向に応じて、DX推進を担う専門部署への配置転換を行っている点です。中には、ソフトウェア開発会社への“越境出向”を経験した社員もおり、中小企業でありながら柔軟かつ実践的な学びの場をつくっています。伝統と革新を両立しながら、社員の“学ぶ力”を丁寧に育てていく姿勢は、多くの企業にとって参考になるのではないでしょうか。
業界も企業規模も異なる3社の取り組みですが、共通して言えるのは、リスキリングを“短期的な施策”ではなく、“未来を見据えた人材戦略”として位置づけていることです。ただ研修制度を設けるのではなく、社員のWILLに寄り添いながら、学びが企業の力に変わる構造をいかに設計するか。そこに、リスキリングの大きな意義を感じます。
企業とNPOの協働事例に見る、社会を巻き込むリスキリング
企業による社員へのリスキリングだけでなく、NPOと連携した社会課題解決型の取り組みも注目されています。特に、社会的に不利な立場にある人々や、学びの機会にアクセスしづらい層に対して、企業が持つ資源やネットワークを活かしながらNPOと共に支援するケースが増えています。
日本IBM「SkillsBuild」|すべての人に、無料で学べる環境を
日本IBMは、無償の学習プログラム「SkillsBuild」を通じて、NPOや自治体と連携し、就労が困難な人々のためのリスキリング支援や、高校生・大学生に向けたスキルアップ支援を行っています。
「SkillsBuild」では、IT・ビジネススキルなど6,000本以上の教材を無料で提供。パートナーとなるNPOは、学習者の選定・サポートや学習後の就労支援などを担っており、IBMはコンテンツとテクノロジー面でのバックアップを行っています。
例えば、社会的養護出身の若者やひとり親家庭の保護者、外国にルーツを持つ方など、多様な背景を持つ人々が対象です。学びを通じて「仕事に就くための選択肢を広げる」ことを目指しており、NPOとの密な連携によって、単なるスキル習得にとどまらない支援体制を実現しています。
サントリーホールディングスのNPO連携|“100年キャリア”を描く機会を社員に
サントリーホールディングスでは、企業内大学「サントリー大学」に「100年キャリア学部」を設置し、社員のキャリア形成支援を行っています。その中で、社外NPOと連携した社会貢献活動プログラムも実施しており、社員が実際にNPOのプロジェクトに参加することで、新たな視野とスキルを獲得できるようになっています。
この取り組みは、単なるボランティア活動にとどまらず、「実社会の課題に触れることで、自身の仕事やキャリアの意味を問い直す」という学び直しの機会を提供するものです。従業員にとっても、企業にとっても、“キャリア自律”の一歩を支える仕組みになっています。
参考:企業内大学「サントリー大学」に「100年キャリア学部」を新設|サントリーホールディングス株式会社
NPO法人G-net|越境学習で企業人に“問い”を持たせる
岐阜県を拠点とするNPO法人G-net(ジーネット)では、都市部の企業人が地方中小企業の課題解決プロジェクトに関わる「越境学習プログラム」を展開しています。
このプログラムでは、大手企業の社員が一定期間、地域企業に入り込み、実際の経営課題に取り組みます。たとえば販路開拓、商品企画、業務改善などが対象で、実務を通じたスキル習得と共に、“越境”によって得られる気づきや視座の転換も大きな成果とされています。
企業にとっては、社員の「学び」と「成長」を促すリスキリングの機会であり、地域にとっては外部人材による支援が得られるWin-Winの関係が築かれています。
企業×NPOの連携によるリスキリング支援は、単にスキルを「教える」だけではなく、「社会課題を自分ごととして捉え、実践的に向き合う機会」を創出しています。リスキリングという言葉が「働く個人」のテーマに留まらず、社会全体の未来を見据えた共助的な挑戦として広がっていくためには、こうしたプレイヤー同士の協働がますます重要になっていくと考えます。
参考:地域発・大企業向け越境学習フォーラム2025 参加者募集!|NPO法人 G-net
リスキリングの「実感」を持つには?
社会課題としての「リスキリング」の難しさは、それが「他人事」になりやすい点です。「自分には関係ない」「今の仕事が続く限り大丈夫」という認識が行動の遅れにつながりがちですが、前述したプレイヤーたちの動きからは、リスキリングとは特別なことではなく、誰もが関われる選択肢であることが見えてきます。
重要なのは、「学び直し」を単なるスキル獲得ではなく、変化する社会を生き抜くための「生きる技術」として捉え直すことです。社会全体のリテラシー向上と、個人一人ひとりが自分自身の働き方をアップデートする視点の両方が必要でしょう。
リスキリングは、構造的かつ社会的な挑戦です。それは必ずしも大きなキャリアチェンジを意味するわけではなく、日々の業務の中で新しい知識や技術を取り入れる小さな一歩から始まります。変化を恐れるのではなく、変化を成長の機会として捉える。そんな視点の転換こそが、リスキリングの本質なのかもしれません。