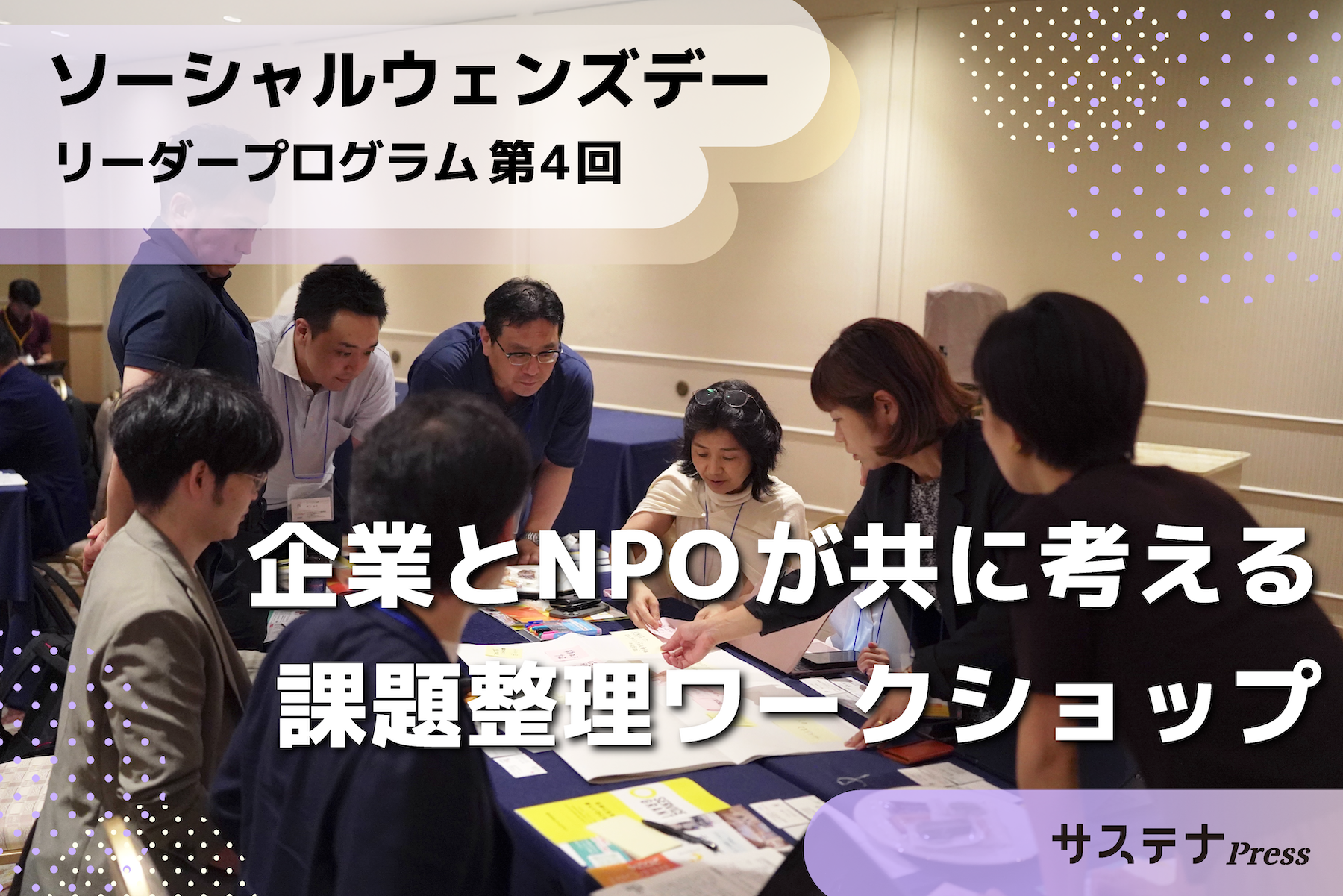経済同友会が主催する「ソーシャルウェンズデー」とは、水曜日を中心に企業人がボランティアや社会貢献活動に取り組む新たなムーブメントの名称です。ソーシャルウェンズデーを通じて、100社1万人のトライセクター人財(民間、公共、市民社会の3つのセクターの垣根を越えて「社会価値」の創造に取り組む実践者)を輩出することを目標としています。
今回は、2025年7月に開催された第4回リーダープログラムにおける、認定NPO法人サービスグラントによる「NPO課題整理ワークショップ」の内容を紹介します。
プロボノで実現する“社会参加先進国”への道
認定NPO法人サービスグラントは、職業上のスキル・経験等をボランティアとして提供し、社会課題の解決に成果をもたらす「プロボノ」活動を推進する団体です。サービスグラントが目指すのは、社会課題を前に、互いの立場や違いを尊重しながら、当たり前のように協働できる社会。日本を、世界を、社会参加先進国にすることをめざして、プロボノの可能性に挑戦しています。
今回のワークショップは、NPOの課題整理と解決策の検討を通じて現場の課題を共有し、企業とソーシャルセクターとの共創のヒントを得ることを目的に開催されました。企業参加者とNPO団体が協働でワークを行うことで、セクターを越えた相互理解と新たな気づきを生み出す場となりました。
認定NPO法人サービスグラント ファウンダー 嵯峨 生馬氏
参加NPO団体が直面する多様な課題
ワークショップには6つのNPO団体が参加し、それぞれが抱える課題が紹介されました。
認定NPO法人CLACK
デジタル教育とキャリア教育を通じて、困難な状況にある子どもが未来を切り拓く力を育む機会を提供。【課題:テクリエさぎのみの活性化や企業連携について】
認定NPO法人こまちぷらす
子育てが「まちの力」で豊かになる社会を目指し、孤立した子育てをなくし、多様な人々が関わりつながる場を創出。【課題:子育てのニーズに対して企業や地域が共創する事業の創出】
一般社団法人チョイふる
足立区でこどもたちが「選べる未来」を持てるよう、食料支援や居場所づくりを行う。【課題:継続的な企業との関係構築】
NPO法人HUG for ALL
児童養護施設でくらすこどもたちの安心できる居場所をつくり、生きる力を育むための機会を提供【課題:資金調達や仲間集めを担うサポーターの体制や運営方法】
認定NPO法人ファミリーハウス
難病の子どもが自宅から離れて入院する際に、経済的負担が少なく滞在できる施設を運営【課題:規模拡大にともなう組織運営方法や意思決定の方法】
NPO法人フェアスタートサポート
社会的養護下の子どもたち・若者たちへの就労支援として、キャリア教育、就職前のサポートやアフターフォローを行う【課題:全国の児童養護施設と企業との連携を実現するための方法】
実践的な課題整理のステップ
ワークショップの流れにもとづき、企業の参加者と各NPO団体は数グループに分かれて各ステップに取り組みました。
はじめに、各NPO団体に質疑を行いながらそれぞれの団体が抱える課題を洗い出し、ある程度課題が出たところで、団体が目指す社会的成果と今後の活動目標について改めて確認しました。これにより、目先の課題解決だけでなく、団体のミッションに沿った本質的な解決策を検討する土台を整えます。
課題の整理ワークでは、中長期的目標に照らして課題を分類し、優先順位付けと解決の方向性の二軸で整理。どの課題から着手すべきか、どのような方法で解決すべきかを明確に可視化しました。
その中から解決策を具体的に検討する課題を一つ選び、できるだけ多くのアイデアを出すことを目指します。企業参加者の視点が加わることで、斬新な解決策も生まれる場面もありました。
最後に、出されたアイデアの中から特に優先順位が高い解決策を具体化し、実際に明日からどういった取り組みをしたらよいか、アクションプランを検討しました。実現可能性と効果のバランスを考慮しながら、具体的な行動計画に落とし込んでいきました。
セクターを越えたプログラムで生まれる新たな視点
ワークショップ終了後、参加者からは多くの学びと気づきが共有されました。
「直接NPO主催者の話を聞くことができ、運営にかかわる課題を企業とは違った視点を発見しながら確認することができた」「プロボノの機会が、自己内省や視野の拡大につながると思う」「組織課題というのは、規模の大小にかかわらず共通していることが多いのだと改めて実感した。複数の第三者からの視点が入るというプロセスに非常に意味があると感じた」などの声から、現場の生の声に触れることで、社会課題の実態をより深く理解する機会となったことが窺えます。
また、NPO団体へのアンケートでは「企業側の視点や目線を改めて知ることができ、今後の伝え方や表現方法を工夫する上での大きなヒントを得ることができた」「我々がもっている資源のなかで活かしきれていない財を皆さん視点であぶりだしていただき、既存提案資料や素材もみていただいた上で、どんな企業にどんなテーマでどのように提案をするとよいかの具体アドバイスまでいただけた」といった感想もありました。
NPO団体が持つ社会課題への深い理解と現場での実践知に、企業の持つ経営やビジネスの視点・スキルが加わることで、単独では実現困難だった解決策や、持続可能なアプローチの可能性が感じられる時間となりました。
次回のソーシャルウェンズデー リーダープログラムでは、今回参加いただいたNPO団体の各現場を訪問するワークショップを開催予定です。サステナPressでは、引き続きプログラム内容をご紹介するとともに、トライセクター人財の活躍や共創事例、これからの社会課題解決の新たな形を探っていきます。