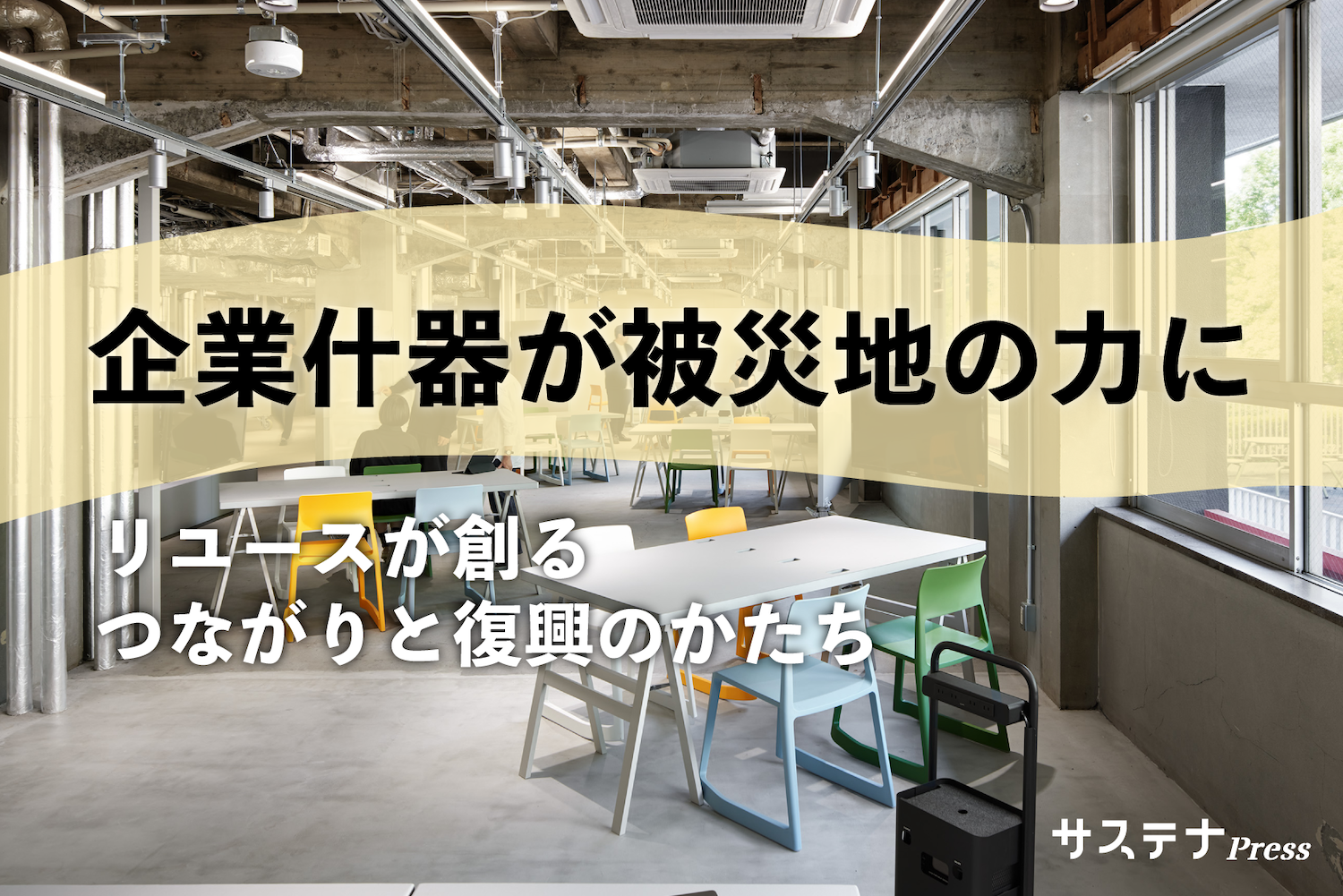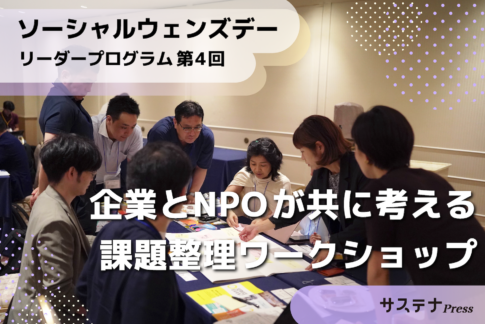能登半島地震から一年半が経つ現在も、復興への道のりは続いています。そんな中、2025年に実施されたリクルート社の什器寄付プロジェクトを通じて能登に渡った什器は、現地のNPOや企業の拠点で活用され、コミュニティ再生を支えています。
本記事では、廃棄されるはずだった什器の寄付プロジェクトについて、寄付を受けた現地団体の声を通して紹介します。
(インタビューは2025年5月時点の内容になります。)
目次
企業什器の寄付プロジェクト
リクルート社の什器寄付への想い
株式会社リクルートでは、毎年多くのオフィスのリニューアル・統廃合・移転等を実施しています。実施に当たっては、転用し使い続けることを基本としている中、面積縮小や機能変更により、余剰となる什器が発生します。
それらの什器の中にはまだ使用できるものが多く含まれており、これらの什器を世の中の必要としている企業・団体に寄付することで、循環型社会の形成や社会貢献ができると考え、オフィスの工事で排出される余剰什器に着目したのが、今回のプロジェクトの始まりです。
同社は「マッチング&ソリューション」を事業の一つとしており、本プロジェクトを単なる寄付ではなく、多くの方とのつながりを作ることができる機会としています。寄付から始まった関係がつながりの機会となり、やがてより大きな活動となっていく「循環」の仕組み。この活動が世の中に広まり、企業にとって「寄付→循環」という選択肢が当たり前になっていくことを願っています。
什器寄付プロジェクトの流れ
今回の什器寄付プロジェクトでは、ICHI COMMONSが運営する「サステナNet」において募集を実施。また、ICHI COMMONSのネットワークからも寄付先候補団体の紹介を受け、幅広い視点からニーズを把握することができました。
企業とNPO、被災企業とのマッチングでは、単に什器を送るだけでなく、それぞれの団体が抱える課題や活動内容を深く理解することを重視しました。現地で活動するNPOや企業へのヒアリングを行い、現地の状況や今後の展開も考慮に入れ、長期的に活用してもらえるマッチングを心がけました。
寄付先が決定した後は、リクルート社が保有する什器リストを提供し、各団体のニーズに応じて選択してもらう方式を採用。個数制限は設けず、本当に必要としているものを選んでもらうことで、復興・運営に十分活用いただけるような寄付を実現しました。
寄付先の声
ごちゃまるクリニック|地域医療の現場から生まれた、子どもたちの新たな居場所
寄付先のひとつは、輪島市で地域医療を展開するごちゃまるクリニックです。診療所のある建物の1階では多職種によるプライマリケアを提供し、2・3階ではNPO法人じっくらあとが10代の居場所づくりの一環で「わじまティーンラボ」を運営しています。能登半島地震では建物の修繕が必要となったものの、実は2024年9月に起きた豪雨災害の方が甚大な被害をもたらしました。
「床上90センチの浸水で、1階の什器はすべて泥まみれになり廃棄せざるを得ませんでした。5月に再開したばかりでしたが、10月から2階のスペースを間借りする形で外来診療を続けています」と、ごちゃまるクリニック副院長・NPO法人じっくらあと理事長の小浦さんは当時を振り返ります。
震災後はラボの利用者が増加したと話す小浦さん。公園が仮設住宅となり、友達の家への行き来も難しくなった子どもたちの居場所が激減。そんな中、3月末に再開したラボは、放課後の貴重な居場所となっていました。
今回寄付を受けた什器は、テーブルや書類棚が約5個、椅子約20脚など。間借りしているクリニックの事務スペースでは機能的なオフィス家具が、ラボでは子どもたちがリラックスできる一人掛けソファーや丸テーブルが活用されています。
小浦さん「スタッフが大変な中でも働いてくださっているので、少しでも環境を良くしたかった。パイプ椅子で何とかしていたところ、きちんとした椅子に変えられたことは本当にありがたかったです」

また、什器寄付の意外なメリットとして、小浦さんは選択のストレス軽減を挙げます。
小浦さん「混乱の中、自分たちで一つひとつ必要なものを選ぶ作業は案外大変です。今回は頂いたリストの中から什器を選べたので、ゼロベースで選ぶよりもストレスが軽減できました。間借りスペースでの活用だったので、事務スペース用の什器を選びやすかったのも良かったです」
合同会社CとH|能登で「始める人、続ける人」を増やすインキュベーションコミュニティ
もうひとつの寄付先となったのは、珠洲市で24時間運営のコワーキングスペースを運営する合同会社CとHです。震災の半年前に立ち上げたばかりの同社は、「地域丸ごとパラレルキャリア」をビジョンに、関係人口を巻き込んだ地域活性化に取り組んでいます。
代表の伊藤さんは「震災があったから課題が生まれたわけではない。人口減少など元々あった課題が、震災により10年、20年分早まっただけ」と語ります。震災後は支援者や新たなビジネスを模索する人々が急増。しかし、深刻な住宅不足が活動の障壁となっていました。
伊藤さん「能登で何かやろうと思っても住む場所がない。そこで建物を借りてシェアハウスを立ち上げました。シェアハウスがなかったら来れなかった学生や起業家たちが、今ここを拠点に活動しています」
今回寄付された什器は100点以上。メインのシェアハウスではリビングのテーブル・椅子、和室のソファーとして、コワーキングスペースではテレフォンブース、アクセサリー工房では作業用の椅子や書類棚として活用されています。

伊藤さん「コワーキングスペースとして必要な機能が揃えられていませんでしたが、テレフォンブースなどの環境が整ったことで、東京のビジネスパーソンが来やすくなりました。本業を持ちながら能登の復興に関わる人を呼び込めるようになったんです」
また、什器寄付ならではの価値について、興味深い指摘もありました。「お金をもらっても同じものは買わないと思います。”もの”として残ると、ストーリーが語りやすい。『この机はリクルートさんから寄付されたんです』など、利用者に対しても、いろんな人の善意や協力でここが成り立っているという話ができます」
最後に、今後の支援のあり方について伊藤さんはこう提案します。
伊藤さん「これから店舗を再建したり、新たな人が進出してくるタイミングになるので、什器の需要は引き続きあると思います。現地の活動を継続するために、例えば企業の新規事業研修を現地で実施するような、持続的なプロジェクトなども発生していくと良いですね」
企業什器寄付が拓く新たな支援のかたち
被災地のニーズは刻々と変化する中、什器寄付プロジェクトは、その変化に寄り添いながら、復興の基盤を支える新たな支援の形を示しています。
ICHI COMMONSでは、今回の事例をモデルに、より多くの企業と被災地をつなぐ仕組みを広げていく予定です。企業什器寄付の取り組みは継続して実施予定で、今後の募集については「サステナNet」を通じてお知らせします。
被災地支援に関心のある企業の皆様、什器寄付を希望される団体の皆様は、ぜひこちらまでお問い合わせください。